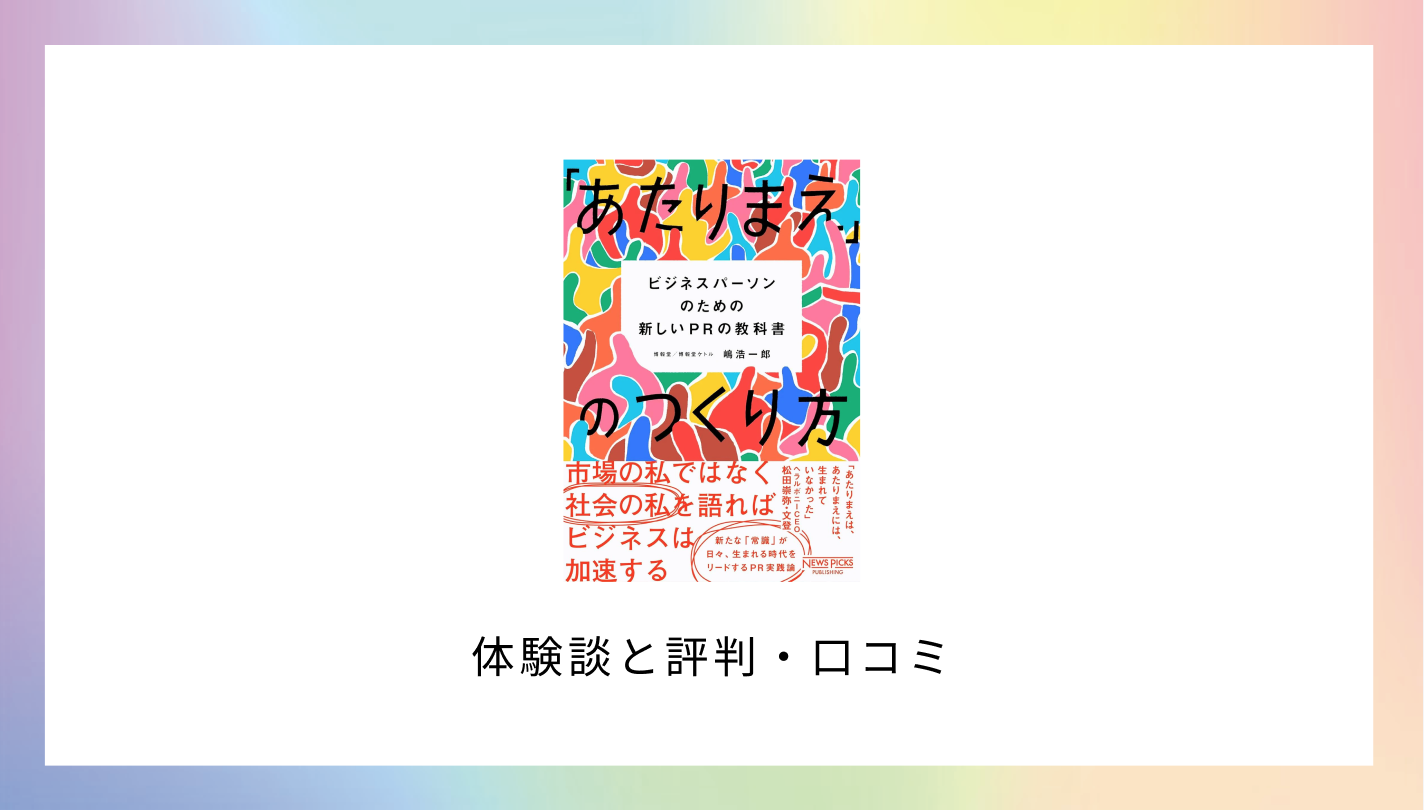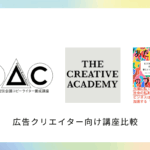コピーライターとして言葉に向き合う中で、「いいコピーを書くだけでは届かない」と感じることが増えてきました。
広告は見られず、SNSは流れ去り、情報は届く前に埋もれていく。
その中で、言葉を“拡散させる仕組み”や“文脈の乗せ方”を体系的に学んでおきたいと感じ、嶋浩一郎さん主催のPRパーソン養成講座を受講しました。
この記事では、講座の概要や登壇者、課題の内容、受講後に得られた視点についてまとめています。
講座の概要|全10回/全国開催/青山ブックセンター経由で申込(※現在は独立)
受講した当時は、青山ブックセンターを通じて申し込みました。
現在は、講座運営をしていた担当者の方が独立しており、別の運営体制になっているようです。
講座は全国各地で約10回開催され、各回に講師が登壇する形式です。
他の講座と異なり、チーム課題などはなく、個人参加でのアウトプットになります。
初回講義|「PRとは、社会記号をつくること」
第1回の登壇者は、嶋浩一郎さんと、あるメディア編集者の方でした。
嶋さんは講義の冒頭で、こう語ります。
「PRとは、プレスリリースを書くことではなく、“社会記号”をつくることです」
この言葉が、この講座の全体テーマを象徴していると感じました。
情報をどう広げるかではなく、“社会のどこに刺すか”を考える。
その考え方に、広告ともマーケティングとも違う、新しい広がり方を感じました。
講座の構成|各メディア編集者 × 実戦型PR戦略課題
講座の各回では、女性誌・Abema・週刊文春など、さまざまなメディアの編集者が登壇します。
毎回、その編集者が「メディアとしてどういう視点で記事や情報を扱っているか」を語り、
それを踏まえて「そのメディアに取り上げてもらうためのPR戦略」を考える課題が出されます。
つまり、
- 講義→各メディアの構造や編集方針を知る
- 課題→その文脈に合った情報の見せ方を考える
という繰り返しです。
課題に対して提出がある回とない回がありますが、毎回**“メディアとどう関係を築くか”を考えさせられる内容**でした。
後半は「視座を上げる」フェーズへ
講座後半では、博報堂のPR系クリエイティブディレクターや、現役インフルエンサーなどが登壇します。
前半で“メディア構造”を理解したうえで、どう戦略的に広げるか/どんな物語を設計するかという視座が求められます。
特に印象的だったのは、近年登壇していた鳥羽周作さん(sio)。
嶋さんと親交があるため、PRやメディアとの関わり方、セルフブランディングについての話が中心でした。
チーム課題はない/仲間との熱量は講座次第
この講座では、宣伝会議やTCAのようなチーム課題はありません。
そのため、「講座を通じて仲間と何かを作る」という一体感は薄めです。
とはいえ、期によってはLINEグループが活発だったり、飲み会で盛り上がることもあります。
ただし全体としては**“個人で学びに来ている人が多い”講座**という印象でした。
ポイントまとめ:
- チーム課題やメンター制度はない
- 人間関係の密度は講座の熱量次第
- ただし、内容自体は個人の学びとして非常に濃い
コピーライターがなぜこの講座に通ったのか?
もともと筆者はコピーライターとして、広告やブランディングに携わっていました。
ただ、近年「言葉は作れるけど、広がらない」という感覚が強くなっていました。
- いいコピーを書いても、見られない
- SNSに出しても、流れていく
- 広告というより“現象”をつくりたい
そんな感覚を持っていた中で、PRという「言葉を広げる仕組み」の学びに触れておきたいと思ったのがきっかけです。
実際に得られた視点|PRの最終ゴールは“社会記号”をつくること
講座の中で印象的だったのは、「PRのゴールは“社会記号”をつくること」という考え方です。
- メディアに載る
- SNSでバズる
- 検索される
こうした状態の“先”にあるのが、「社会にある言葉や現象として定着する」こと。
それはPRに限らず、広告・マーケティング・コピーライティングすべてに通じるゴールだと感じました。
この講座が向いている人/向いていない人
向いている人:
- コピーは書けるが、広げる力を学びたい人
- 企画・PR・コミュニケーションに関心がある人
- インハウスでPRの内製化に関わっている人
向いていない人:
- 未経験でこれからコピーを学びたい人
- 仲間との熱量を求めている人(TCAや宣伝会議の方が向いている)
- 添削や実践課題で伸ばしたい人(この講座は理論と視点寄り)
コピーライター視点での結論|“武器を増やす”ための一歩にちょうどいい
この講座を経て、「書くだけでは足りない」時代に、広げる視点・仕組み・思考の引き出しがひとつ増えたと感じています。
未経験者にとってはハードルが高いかもしれません。
けれど、ある程度コピーを書けるようになった人、
またはコピー以外の“戦略・拡散”まで手を伸ばしたい人にとっては、
次のステージに登るための“視座を上げる講座”になるはずです。