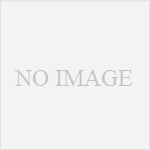この話は、劇的な成功ストーリーではありません。
広告賞を取ったわけでも、若くして引き抜かれたわけでもない。
(※実際には受賞歴もありますが、それは後半に触れます)
でも、「好きなクリエイティブで課題を解決する仕事をしたい」と思ったところから、
ちゃんと現実のものにしていった過程です。
いまはインハウスでコピーを書いています。
未経験から広告代理店のコピーライターになり、そこから2回目の転職を経て、ようやく今の形に辿り着きました。
この記事では、その過程と、考えてきたこと、変わったこと、そして変わらなかったことをまとめておきます。
最初のきっかけ|“カッコよさ”と“人を動かす力”に惹かれた
最初のキャリアは、広告とはまったく関係のないBtoBの営業職でした。
数字に追われるというより、業務量が多く、終電帰りが当たり前。
気づけば毎日が“こなす仕事”で終わっていました。
そんな中で、たまたま社内でデザイン発注をする機会がありました。
外注先が仕上げてくれたポスターを見た瞬間、「これ、普通にカッコいいな」と思いました。
それが、最初に“つくる仕事”に惹かれた瞬間です。
さらに思い出したのが、学生時代に作った学園祭の映像。
簡単な動画でしたが、たくさんの人が笑ってくれて、あの時の高揚感がずっと残っていました。
課題解決への憧れと、クリエイティブの可能性
営業職としての仕事にもやりがいはありました。
人から頼られて、課題に対して提案して、感謝される。
「人の困りごとを解決できる」という構造自体には、強く魅力を感じていました。
だからこそ思ったのが、**「好きなクリエイティブで課題解決ができたら最高だな」**ということでした。
コピーに絞らず、まずは“つくる”ことに関わる
最初からコピーライターを目指していたわけではありません。
当時は「そもそもどうやってなるのか」も分からなかったので、
まずはIllustratorを独学して、外注予定だったポスターなどを社内で内製し始めました。
小さなことでも、“誰かに見せるためのものを自分が作る”という経験は大きく、
徐々に「表現を仕事にする」ことが現実味を帯びてきました。
ただ、デザインだけでは課題の本質に対して手が届かないと感じることも増え、
次のステップとして選んだのが、宣伝会議コピーライター養成講座でした。
宣伝会議コピーライター養成講座で得たもの
受講したのは専門コース。
毎回課題が出て、コピーを書いて、講評を受けるというシンプルな形式でしたが、
ここで得たのは「書く力」よりも、“考える視点”の大切さでした。
自分のコピーには、ターゲットの解像度が足りない。
課題の本質をつかみきれていない。
そうした“ズレ”を、講評を通じて痛感しました。
評価が出る回では、大学生が1位になることも珍しくなく、
経歴ではなく、コピーで勝負する場だったのも刺激的でした。
講座後には、宣伝会議裏の居酒屋“中西”で、深夜までコピー談義をするのも恒例で、
そうした空気感の中で、「言葉で食べていく」覚悟が固まっていきました。
広告代理店への転職|“通す”コピーの現場へ
宣伝会議での課題や、自主制作したコピーをポートフォリオにまとめて、転職活動を始めました。
評価されたのは、「書いたコピー」ではなく、
「なぜその言葉を選んだのか」の説明ができていたことだったと思います。
無事、中堅規模の広告代理店に入社。
コピーライターとして配属され、実案件を担当することになりました。
実際の業務は想像と違い、コピーを書く時間よりも、構造を設計する時間が圧倒的に多い。
打ち合わせ、資料作成、プレゼン、修正。
求められるのは「うまい言葉」ではなく、**“通す言葉”**でした。
2回目の転職を考えた理由|会社も自分も、クリエイティブを信じられなくなっていた
しばらくして、違和感が芽生えました。
会社が徐々にクリエイティブの力を疑い始めたように感じたのです。
「それ、AIでいいんじゃない?」
「コピーってもうそんなに価値あるの?」
そう言われる機会が増えてきました。
同時に、自分自身も、**“このまま書き続けて意味があるのか”**という不安を抱えていました。
そんなとき、見つけたのが**GOが運営するTCA(The Creative Academy)**でした。
もう一度、自分を試したいと思い、エントリーしました。
TCAで取り戻した自信とクリエイティブへの信頼
TCAは半年間の選抜講座。
テーマは毎期変わり、広告/コピー/事業/未来などの軸で進みます。
グループ課題ではGOの現役CDがメンターとしてつき、
課題ごとにチームで企画し、プレゼンまで仕上げます。
そこで出したアウトプットは、すべて上位評価を獲得しました。
この講座で得られたのは、「まだやれる」という自信と、
「クリエイティブを信じている人たちが確かに存在する」という事実でした。
インハウスへ|ブランディングと言葉の“設計”を担う仕事へ
2回目の転職では、インハウス(事業会社)へ。
現在は、ビジョン・ミッション・バリューなどのブランドの根幹を支えるコピーワークや、
テレビCMやプロモーションのクリエイティブ戦略立案〜ディレクションを担当しています。
業務の多くはディレクションですが、コピーも書いています。
正直、「自分が書けなくなった」と感じることもありました。
でも、クライアントに任せるのではなく、自分が決めることの重みと自由がある今の仕事は、
ある意味で最もクリエイティブだと思っています。
自分のコピーがCMになったときのこと
ある案件で、自分が考えたコピーがそのままテレビCMでオンエアされました。
音楽が流れて、映像が動いて、自分の言葉がナレーションとして響いたとき、
正直、今までで一番感動した瞬間でした。
自分の仕事が社会に出ていく感覚。
それが人の記憶に残るかもしれないという実感。
この仕事を選んでよかったと思えた瞬間です。
コピーが、事業を後押しした経験
また別の案件では、コピーが社内・社外の両方で評価され、事業の後押しになったことがありました。
「言いたかったことが、ようやく伝えられた」
そうクライアントに言われたとき、
クリエイティブ=課題解決という軸がまたひとつ強くなった気がしました。
コピーライターとは、表現で課題を解決しようとする人のことだと思う
たまに「言葉が好きなんですね」と言われますが、
正直なところ、言葉そのものが好きなわけではありません。
自分が好きなのは、“表現で課題を解決する”というプロセスです。
何かに向き合い、伝え方を考え、構造をつくり、誰かの行動を変える。
このメディアをつくったのも、クリエイティブの発想がそのまま事業になった例だと思っています。
まとめ|書けるかどうかは、書きながら決めればいい
未経験から始まって、広告代理店、インハウスへとキャリアを重ねてきました。
最初から分かっていたわけでも、うまくいったわけでもありません。
でも、書き続けて、考え続けて、選び続けてきたことで、
「コピーで課題を解決する」ことが、今では自分の仕事になっています。
書けるかどうかは、書きながら決めればいい。
これから目指す人にとって、そう思えるひとつの事例になればうれしいです。